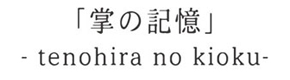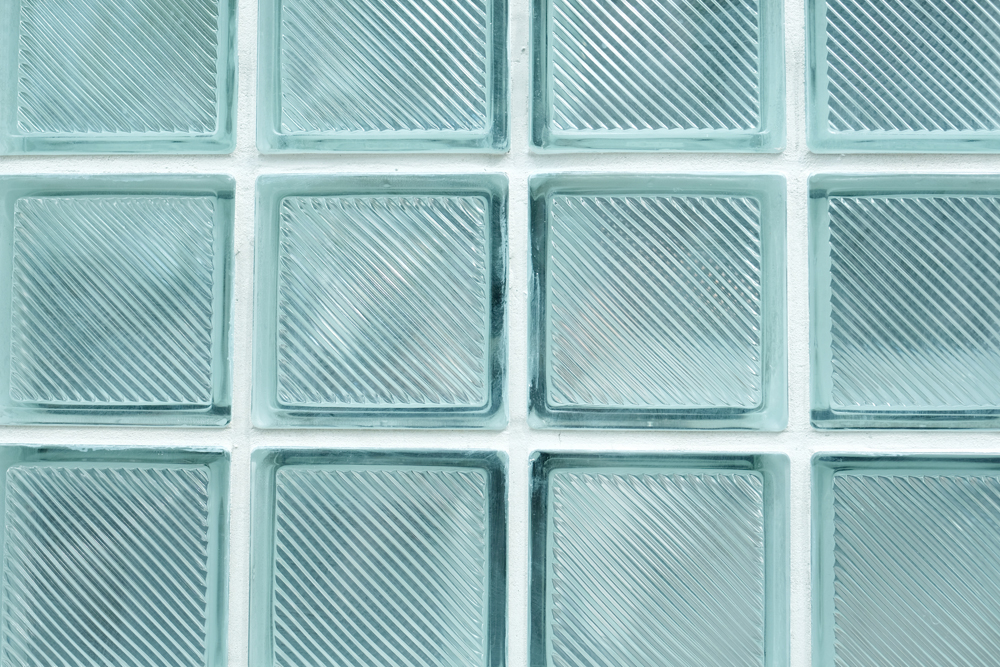おばあさまの人生
「実はおばあちゃんが入院して」と、高校時代の同級生、裕賀さんから相談をもらったのは、2019年7月末のこと。今年で91歳になるおばあさまが急な病気で入院し、心配な状態だという。お見舞いに行く度に昔のこと、今のことを話してくれるおばあさまの人生を、何らかの形で本に綴じてもらえないだろうか?という相談だった。
裕賀さんがおばあさまを想う気持ちと、病状や体力を想像しながら。無事退院されて体調も少し落ち着いたという9月頭、裕賀さんの帰省のタイミングに合流。おばあさまのお話と、この秋にリフォームで内装が変わることが決まったというご実家の今。裕賀さんが綴り残したいと感じている二つの記憶を「掌の記憶」として一つにおさめてお贈りするという形になった。


震度7にも耐えたお家
元々はとある建築家が設計し、暮らしていたというお家。裕賀さんのお父さまが見つけて、1994年に越してきた。翌年は阪神・淡路大震災。震度7の揺れにも耐え、今年で築32年になる。
「打ちっぱなしの壁とか、こだわりのところが塞がれてしまうの」裕賀さんの案内で、変わってしまうところを中心に写真におさめる。鉄筋と木造が半々。中心を螺旋階段が巡り、洋と和、石と木、光と影…さまざまなコントラストが本当に美しい空間だった。
「自分の思うような自分らしくを体現できるようになる前の記憶の場所だったから」と、暮らしていた頃を振り返りながら「でも写真のおかげで、冷静に好きになれた気がする」という言葉をくれた。この家が抱く美しいコントラストは、裕賀さんの感性のルーツの一つのように感じた。

混沌が渦巻く町
ご実家の撮影を終え、隣駅で暮らすおばあさまの元へ。道を歩きながら、裕賀さんが今日まで聴いたおばあさまの記憶を振り返る。神戸の下町で生まれ、神社などの建築に携わる家で育ったというおばあさま。「海外から色々な文化が入ってきた港町の活気ある戦前の神戸で、何事かを起こしていた人が先祖にいた」というところに、勇気が湧いたのだという。
おばあさまから聴いた話を頼りに、先祖が建築に関わった湊川神社の神主さんの元も訪ね、当時の神戸の活気に触れることもできた。「神戸ってなかなか混沌としていて、エネルギーが根底にあっておもしろいところなんだなと」自分のルーツである「神戸」に惹かれる裕賀さんの気持ちが、言葉の端々から伝わってきた。

「香川組」のお嬢さん
家に着くとおばあさまが笑顔で迎えてくださり、早速本題に。「お嬢さんだったんでしょ」という裕賀さんのリードで戦前の神戸の町へ、記憶の旅が始まった。
おばあさまの祖父にあたる「次八さん」が徳島から神戸に出てきて立ち上げた「香川組」。長田神社や湊川神社の建築も請負い、新開地にあった聚楽館という建築物の移築なども請負った。広い家の2階には地方から働きにきた若い衆が大勢いて「お嬢さん」として皆から可愛がってもらっていたという。
「うちの若い衆が年いって辞めて。家の横にようけ店出とってん。せやから行ったらただでくれんねんな。窓から『おっちゃんくれー』言うたら持ってきてくれる訳」おばあさまの記憶から、当時の建築を担っていた職人たちの様子が伝わってくる。

大空襲のそのあと
初代・次八さんの跡を継ぎ、息子の喜之八さんが二代目に。喜之八さんの娘だったおばあさまは、四姉妹の長女。「おばあちゃんが継いでたら面白かったのにね」と、裕賀さんが語りかけると「私、継ぐ予定やってん。やけどあかんわ。戦争で皆焼けてしもた。家も、家建てる道具も」と、おばあさまの声が続いた。昭和20年3月に起きた、神戸大空襲のことだった。
焼夷弾が落ちてきたのは、妹さんが生まれて2日後。お櫃一杯のご飯とおしめ、戒名を持って逃げ、何とか助かった。妹たちは徳島へ疎開し、17歳で会社に勤めていたおばあさまは喜之八さんと神戸に残ったのだという。「戦争は怖いな。あんなんよう生きとった思うよ」その一言にこめられた想いを、静かに受け取った。

記憶やルーツを辿る旅
まだまだ聴きたいことはあったけれど、お話を聴き始めて2時間半が過ぎた頃、おばあさまの体調を考えて一区切りに。90年という長い人生からすると、きっとまだほんのひと欠片。でもこの記憶の欠片が、さらなる記憶の呼び水になるように。そして「家族の記憶や自分のルーツを辿る旅」の一つの形として。ここに贈ります。

取材後記
高校の同級生でもある、画家の裕賀さん。お互い阪神・淡路大震災後の町で育ち、結婚を機に地元を離れて暮らしていた頃再会しました。人の「心」を大切に絵を描く裕賀さんと、人の「記憶」を綴じる私。動機や表現方法は異なるものの、人のルーツに触れたり、何らかの形でのこして共有してゆくことに強い関心を持っていました。
おばあさまを想う気持ちからお声がけいただいた、裕賀さんのルーツを辿る旅。「『この子だけは孫じゃなくて相棒』と言われたのが嬉しかった」という裕賀さんの言葉のとおり、祖母と孫という関係以上の、ルーツを共にする同志のような関係性を感じる場面が何度もありました。このささやかな記憶が、さらなる記憶の呼び水になるように「掌の記憶」として贈ります。
Writing,Photo :藤田理代(michi-siruve)
2019年9月取材